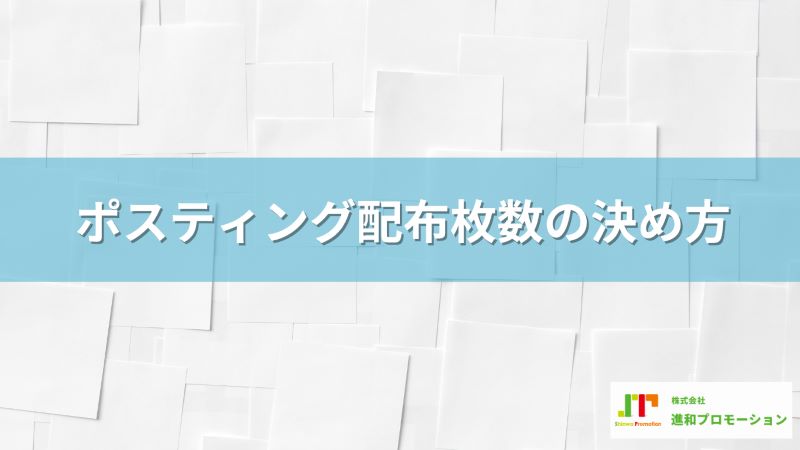ポスティングはSTP分析をせずにペルソナ設定は効果が半減!

目次
ポスティングにおけるSTP分析の大切さ
ポスティングを成功させるには、まずSTP分析が欠かせないという話をすると、「それは大企業のマーケティング担当者が使う難しいやり方なのでは?」と身構える方がいらっしゃるかもしれません。実際のところ、この分析は規模の大小を問わずビジネスを伸ばすために有用です。
STP分析のうち、はじめの「セグメンテーション(Segmentation)」では、市場を細分化しながら潜在顧客の傾向を洗い出す工程を踏みます。たとえば商圏内の年齢別人口構成を調べ、学生が多いエリアなのか単身赴任のビジネスパーソンが多い町なのかを把握できれば、配布するチラシのデザインも確実に変わってくるのではないでしょうか。
さらに次の「ターゲティング(Targeting)」では、複数のセグメントの中から効果的にリーチできる層を選定します。ここは競合他社との違いを意識する場面でもあります。たとえば、すでに大手が取り込んでいる顧客層を無理に狙うよりも、まだ未開拓の層や地元密着の特色を生かしやすい顧客群を選ぶほうが賢明なことが多いです。
そこで最後の「ポジショニング(Positioning)」により、自社がどんな立ち位置で勝負し、どう差別化を図るかを整理します。少人数の家庭向けに特化した品揃えをPRするのか、あるいは日常必需品を幅広くカバーする店と位置づけるのかを明確に打ち出せば、伝えるべきポイントが定まりやすくなります。
STP分析の重要性は、ポスティング全体の設計を左右する点にあります。マーケティングの世界では「先に戦略ありき」と言われますが、配布戦略も同じです。なぜなら、どこへどのチラシをまくかを見誤れば、発注コストや制作コストが徒労に終わる可能性が高まるからです。
実際、小さな商圏であっても、STP分析を行い配布エリアを絞ったところ、問い合わせが倍増したという中小企業の例もあります。ポスティングは広範囲にアプローチできる反面、闇雲にまくと配布ロスが発生しやすい手法です。STPをしっかり意識するだけで、そのリスクを格段に低減することが期待できるでしょう。
進和プロモーションでは、配布地域に関する相談を承っております。
ポスティングに関するご相談はお気軽に!
0120-044-095
ペルソナ設定の前にSTP分析が必要な理由
最近ペルソナを設定する有効性については、多くの方が認識していますが、ペルソナ設定をする際に、もしSTP分析のプロセスを経ずに「とりあえずこんな人に来てほしい」とイメージを作り込もうとすると、本来狙いたかった層とのずれが生じやすいです。
ペルソナは「ある特定の人物」を象徴として設定し、その人の趣味や行動パターンを細かく描写することで、実際の顧客を強く意識できるようにする手法です。ところが、この手法が有効に働く前提として「どの市場からどんな顧客を優先的に取り込むか」が明確になっている必要があります。それを整理するのがSTP分析であり、十分なデータと検討が伴わないままペルソナを描くと、たとえばファミリー向けの商品なのに単身赴任者向けのイメージになっていたり、シニアに特化したサービスなのに若者の利用ケースを前面に押し出してしまったりするミスマッチが起きるわけです。
こうした違和感は、ポスティングの現場でも大きな影響を及ぼします。たとえば、実際には子育て中の世帯向け商品が主力なのに、チラシを配るエリアを学生街や単身者用マンションが集中している地区に絞ってしまうと、目標とする反応を獲得できる確率が下がってしまいます。これはデザイン面でも同様で、実際には年齢層が高めのお客さまのハートをつかむべきなのに、若者ウケしそうなポップでカラフルなデザインに仕立ててしまうと、結果として響かない印象を与えかねません。
STP分析を行ってからペルソナを作り込む流れであれば、「この地区には30代後半から40代のファミリーが多い」「同じような主力商品を出している競合が少ない」という事実をもとに、子育ての悩みにフォーカスしたペルソナを組み立てられます。そうなれば、チラシに載せるメッセージも「ファミリー向けの使い勝手」や「忙しいお母さんを手間から解放するポイント」などを軸に据えやすいです。ひるがえって、STP分析をスキップしてペルソナを先に決めてしまうと、こういった現実的な方向性が薄くなり、作り手の想像だけで物事を固めてしまう結果に陥ることがあるでしょう。
実践! ポスティングにおけるSTP分析とペルソナ設定の手順
では、ポスティングにおいてSTP分析とペルソナ設定を実践するとき、具体的にどのようなステップを踏むのが望ましいのでしょうか。
1)エリアと顧客の特性を調査
まず最初に取り組むのは、ターゲットエリアの情報収集です。地域の統計データや、自社で過去に行ったチラシ配布の成果記録を参照しながら、たとえば単身者が多い町かファミリー層が中心かなどをチェックします。
そのうえで、年齢構成や家族構成に注目し、広範囲にまくよりも集中的に配布したほうが反応を得やすい地域を抽出するわけです。
2)顧客層を切り分けるセグメンテーション
次にセグメンテーションとして、単身者層、ファミリー層、シニア層など、複数の切り口で候補を整理します。実際には一度で完璧に分類できるわけではないため、仮説を立ててはデータを照合し、マーケットの全体像をより具体的に把握していく作業が必要です。
3)ターゲティングで配布優先順位を決定
ターゲティングでは、抽出したセグメントを比較しながら「どの層に向けてチラシを配るのが最も効果的か」を検討します。もし競合がファミリー層を強力に抑えているならば、そこにぶつけるべきか、あるいは別のニッチを狙うのが得策かを考えるのが戦略の要です。
4)ポジショニングと自社サービスの強みを再確認
これらを経て、ポジショニングを決定します。つまり「ファミリー向けのリーズナブルな日用品が豊富」と打ち出すのか、「働く女性に嬉しいオシャレ雑貨がそろう」と注目を集めるのかを明確化する段階です。ポジショニングが定まると、チラシのデザイン、文言、キャンペーン情報の訴求ポイントに一貫性が生まれます。
5)ペルソナを具体化し、チラシ制作へ落とし込む
そのうえで最後に具体的なペルソナを作成しましょう。たとえば、子育て世帯向けなら「35歳の会社員のご主人と30歳の専業主婦、幼稚園の娘がいる三人家族」というように、詳細な状況を想定してみると、コピーライティングでも「忙しいお母さんの時短を応援」といった具体的なフレーズが出しやすくなります。そして、そのペルソナが興味を持ちそうなビジュアルも自然と浮かんできますから、配布チラシの印象が格段に良くなる可能性があります。
STP分析なしでペルソナ設定するとどうなるか?
STP分析をせずにペルソナ設定を先行すると、まずターゲットの方向性が曖昧なまま進んでしまい、企業が本来狙うべき顧客像にブレが生じます。その結果、ポスティングで配布するチラシの制作段階から混乱が起こる可能性があります。たとえば、デザインの段階で「若者ウケも狙いたいし、ファミリーも呼び込みたいから、全方位にアピールしよう」という方針になってしまうと、中途半端で没個性なチラシができあがるリスクが高まります。万人受けを狙うあまり、誰の心にも強く響かない内容になってしまうのです。
さらに、エリア選定においても、ターゲティングを明確にしていないと「とにかく広い範囲へ大量にまいておけば良い」という方針になりがちです。しかし、ポスティングには人件費やチラシ製作費がかかるため、反応率が低いエリアへ配りすぎるとコストばかりかさんで結果が伴わない展開に陥りやすいでしょう。ペルソナというのは、あくまで「どの顧客層が最重要なのか」をリアルにイメージするための仕組みであって、その裏付けとなるSTP分析がないと絵に描いた餅で終わる可能性が否めません。
たとえば、「A市には子育て支援センターが充実していて、若いファミリーが多く住む傾向がある」というSTP分析から得られた事実を無視した状態で、シニア向けのペルソナを作り込んでしまうと、そのエリアの実態と大きくかけ離れます。結果として、意図した反応が得られにくいばかりか、無駄な制作コストと配布コストが発生します。顧客を想像する行為と現実の需要をすり合わせる場面を飛ばしてしまうことによるロスは、事業規模が大きくなくても相当な痛手になりかねません。このように、STP分析を省いたペルソナ設定は、ポスティングを活かしきれない要因の一つとなってしまうのです。
進和プロモーションでは、配布地域に関する相談を承っております。
ポスティングに関するご相談はお気軽に!
0120-044-095
正しい順番と準備が成果を左右する
ポスティングを活用するうえで最も大切なのは、やみくもにチラシをまくのではなく、体系的な分析と段取りを踏まえて計画を進めることです。
つまり
「STP分析 → ターゲットの絞り込み → ペルソナの詳細化 → 実際の配布」
という順番です。
たとえば、ある中小企業が「若い単身者よりも子育て世帯に焦点を絞ったほうが、自社の商品価値を最大限にアピールできそうだ」という見込みを立てたなら、ペルソナ設定では「3歳児を抱える共働き夫婦で、忙しくて時短商品を求めている」というように明確な人物像を想定できます。そのうえで、チラシのデザインでも「朝の仕度が楽になるグッズ」の写真や、家族がほっこりするようなイラストを取り入れると、受け手の興味を刺激しやすくなるでしょう。
STP分析をバッチリ行うと、配布エリア選びにも一貫性が生まれます。ファミリーが密集している地域の戸建てや、子育て向け施設の近辺に集中させることで、無駄の少ない形でチラシを届けられます。特に、平日中心に配布をするのか週末に集中するのかなど、ある程度の曜日指定も含めて最適化を検討すれば、チラシを手に取ってもらえる確率を上げることにつながります。STP分析とペルソナ設定を行わない場合と比べると、手応えのちがいに驚く方も少なくありません。
実際にこうした正しい順番を踏むと、次回以降の施策をアップデートしやすいのも利点です。何部配ってどれぐらい反応があったかを追跡しながら、想定したペルソナとずれた部分は再度分析して修正していけば、徐々に反応率は高まっていくでしょう。STP分析を疎かにしてしまうと、この調整サイクル自体がぐらついてしまい、「なんとなく費用だけかかっている」という不満が募る原因にもなります。そうした無駄を避けるためにも、まずはSTP分析→ペルソナ設定→配布実践という流れを一度回してみるのがおすすめです。
今からできるアクションステップ
最後に、ポスティングで成果を狙うための実践的なアクションステップを整理してみましょう。はじめに、市場を細分化するためのデータ集めを始めます。行政機関の統計資料を利用したり、商店会や自治会の情報を参照したりすると、おおよその年代構成や世帯数がわかります。これを踏まえて、自社が重視すべき顧客層を仮決定しましょう。たとえば、地元の学校数から「意外と小中学生のいる家庭が多い」とわかるかもしれません。
次に、そのターゲットを想定しながらペルソナをスケッチします。この段階ではまだ仮のペルソナでも構いません。大事なのは、どのような悩みやニーズを抱えそうかを考えることです。商品やサービスが、どんなシチュエーションで役立つのかを具体的にイメージできるようになると、チラシに載せる文言やビジュアルも定まりやすくなります。
そして実際に配布を実施し、反応を分析します。問い合わせや来店数に変化があったか、どの年代層からのアクセスが多いかをチェックすることで、最初に設定したターゲットやペルソナが適切だったかを振り返る材料になるでしょう。たとえば、予想外に若い世代の利用が増えたならば、次回以降はその世代に合わせたデザインを追加検討する価値がありそうです。
こうしてデータをもとにターゲットを再調整し、新たにペルソナを再設定することで、ポスティングの効果は少しずつ積み上げていくことができます。急に大きな成果を求めるよりも、小刻みに仮説検証を繰り返しながら最適化していく姿勢が大切です。STP分析とペルソナをしっかり組み合わせれば、どのエリアへどんなチラシを投下すれば効率的かが、まるで地図を読むようにわかりやすくなっていくでしょう。そうして無駄なコストを減らしながら、必要な人に確実に情報を届けることこそが、ポスティングの醍醐味ともいえます。
ポスティングの相談はどんなことでも大丈夫です。お気軽にご連絡ください!
進和プロモーションは、福岡・大阪・東京エリアを得意とするポスティング業者です。ポスティングだけでなく、チラシの制作も請け負っています。
長くポスティング事業に携わってきたからこそのご提案ができます。
配布のご依頼・ポスティングに関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!
0120-044-095